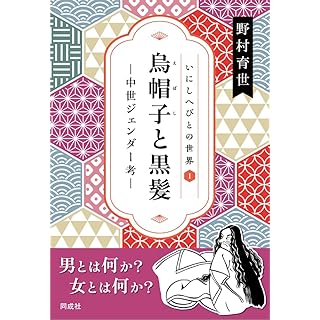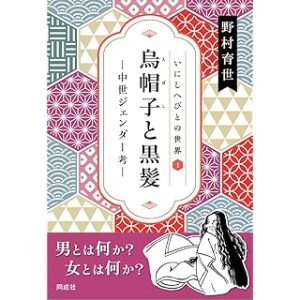 「烏帽子と黒髪: 中世ジェンダー考 (いにしへびとの世界1)」
「烏帽子と黒髪: 中世ジェンダー考 (いにしへびとの世界1)」
(野村育代、同成社)
博打は勝つこともあれば負けることもあります。負けて熱くなって、時には身ぐるみ剥がされることもあるでしょう。
中世の博打を語るときに有名な絵があります。13世紀初めといいますから、鎌倉時代のこと、『東北院歌合』に描かれたもので、博打打ちと思われる男が、着ているもの(ふぐりが見えていますので下帯を含めて)を全て失った素っ裸の状態で描かれているものです。間違いなく、博打に負けたのでしょう。ですが、博打に負けて下帯まで取られながら、この男は烏帽子だけは被っているのです。
(参考)
現在の我々から見れば、かなり違和感のある絵です。しかしながら、それには理由がありました。
結論から言ってしまえば、「中世社会における男とは、冠・烏帽子をかぶったジェンダーのこと」なのです。
ジェンダー(Gender)とは、文化的・社会的に規定された性別の差を含む生物学的性別のことです。要するに、その時代、その社会の「男らしさ」「女らしさ」といっても良いかも知れません。
つまり博打で負けた男は、烏帽子を取る(取られる)と「男」ではなくなってしまうのです。もちろん、烏帽子を取った(取られた)だけで生物学的な意味での「男」でなくなるわけではありません。当時(=中世)の社会的な意味においてということになります。
中世の社会的な意味とは、「男という特権的な身分とジェンダーから転落し、下位身分か異形のモノと化してしまう」ということなのです。
中世社会では、被り物(冠・烏帽子)を被るのが、成人男子の証でしたが、では、女性はどうだったのでしょうか。
本書は、中世日本の「男」と「女」の違いを考察したものです。
目次は以下の通りとなっています。
プロローグ 男とは何か、女とは何か
第一章 男たちの烏帽子狂騒曲
1 元服して冠・烏帽子をかぶる
2 烏帽子が落ちたら一大事
3 寝るときも烏帽子を被ったか?
4 烏帽子と身分制
5 烏帽子のダンディズム第二章 女たちの重い垂髪
1 女の人生と黒髪
2 髪の長さは身分を表す
3 見えない女たち
4 美女か不美女か
5 かづら大作戦第三章 中世に、女であるということ
1 女はつまらない
2 穢の問題と女の仕事
3 女も男も同じ「人」エピローグ 烏帽子と王権
結論から言ってしまえば、「男」の象徴は「烏帽子」で、女の象徴は「垂髪」でした。
第一章が、男と烏帽子について、第二章・第三章が女と垂髪について述べられています。
男も女も子ども時代(「男(おの)童(わらべ)」、「女(めの)童(わらべ)」といいます。)があり、やがて大人(成人)になっていきますが、中世においては、元服という儀式を行って成人となりました。元服というと直ぐに武士を想定しますが、この習慣は、「平安時代の初め、8世紀の貴族社会で始まり、以後、9世紀を通じて皇族・貴族から庶民に至る社会全体に普及した」ようです。
「男童は元服の儀式で初めて髪を上げ、冠や烏帽子をかぶり」「童名から、大人としての実名(じつみょう)が与えられ、男になった」のです。
元服で最も重要な役は、加冠、つまり烏帽子を被せてくれる烏帽子親です。説明するまでもないことでしょう。
では、女性の元服(成人式)はどうだったのでしょう。
男も女も童のときは、髪を切りそろえて垂らした、いわゆるおかっぱ髪でしたが、男はやがて髪を伸ばしてポニーテールに、元服の際は頭上で一本の本鳥(髻)を結い烏帽子を被ります。
男性の元服に対して女性は、裳(も)着(ぎ)(着(ちゃく)裳(も))ということになります。「裳とは、プリーツの入った長いエプロンのようなもの」です。女の正装は「五衣の上に裳と、唐衣という短い上着を着用した姿」なのです。
しかしながら、裳着が始まったのは10世紀になってからで、9世紀までは髪を上げて笄をさす(加笄(かけい))儀式だったようです。
同時に「さがりば」を作ります。「さがりば」とは、「顔の両側の鬢の髪を、肩から胸ぐらいの長さに削いで垂らした」ものです。その他の髪は、垂髪にして長く伸ばすこととなります。女の髪の長さは、高貴さと美しさを表すものだったのです。
男女ともに元服の年齢に決まりはなく、14歳ぐらいが多かったようです。
では、男と女の元服のその後の違いは何でしょうか。それは、男は元服と同時に「天皇を頂点とする官職体系の中に位置づけられ、国家機構の成員になるのだが、そこにポストを得る女はごく一部であって、ほとんどの女は外部におかれたままだった」ということです。
男は公人となりますが、女はそうではなかったということになります。
なお、裳を使わない庶民の女性はどうだったのでしょうか。「しびら」というエプロンのような布がありますが、それが裳の役割を果たし、垂髪を元結で束ねるようになり、身分が高ければ髪も長く、元結も下になるのではないかという説を著者は紹介しています。
男の元服は、烏帽子を被ることだとありますが、では男は寝るときも烏帽子を被ったままだったのでしょうか。
中世では、女は伸ばした髪で顔を隠し人前に素顔をさらさないといわれていますが、宮仕えの清少納言などはどうしていたのでしょうか。
また、「髪は烏の濡れ羽色」という言葉があり、美しい黒髪は女の象徴のように言われますが、では縮れ毛の女性はどうしていたのでしょうか。
そうした興味深い考察が展開される本書は、読んでいて思わず引き込まれてしまいます。
男性が女として、女性が男として育ち、成人後に本来の性にもどる「とりかえばや物語」が紹介されていますが、日本では昔からジェンダーの問題が取り上げられていたのですね。
また、最初の博打の男に戻って、烏帽子を取ることが、「下位身分か異形のモノと化してしまう」とありましたが、大江山の酒呑童子を「童子」と呼ぶのも酒呑童子が、烏帽子を被っていなかったからだと思われます。鬼の統領とも盗賊の統領ともいわれますが、盗賊に煩わしい烏帽子は不要でしょうし、烏帽子を被らない異形のモノとして鬼と形容したのではないでしょうか。成人の男性と認められないことから、「童子」と名付けた、あるいは名乗った、ということではないでしょうか。
江戸時代に盗賊を「〇〇小僧」と呼ぶのもこの流れかなと思っています。
今回も関連する小説は紹介できませんが、何だか「とりかえばや物語」を読んでみたくなりました。古文を読むのはちょっと苦手、という方のために朗読を聞くというのはいかがでしょうか。以下(↓)で聞くことが出来ます。