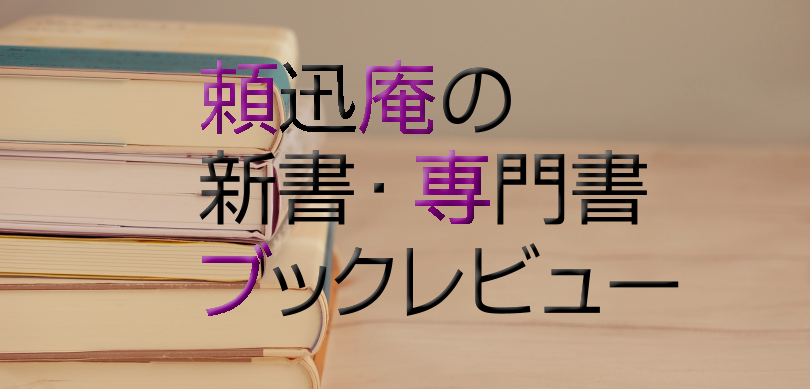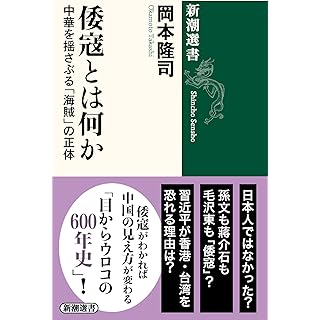 『倭寇とは何か ―中華を揺さぶる「海賊」の正体』
『倭寇とは何か ―中華を揺さぶる「海賊」の正体』
(岡本隆司、新潮選書)
本書のタイトルを見て、倭寇について書かれた「日本史の本」だと思い、購入して読み始めました。
でも、違ったのです。本書は、東洋史の研究者が、明代以降の中国の通史(あるいはその解釈)について書かれたものだったのです。
とはいいながら、読み始めるとその内容は独特で、非常に興味深いものでした。あっという間に読み終えていました。
周知のように「倭寇」とは、中国や朝鮮の側から使用された言葉です。なぜ、それが歴史用語として定着したのか、わたしにはよく分かりません。改めて考えれば、中国史や東洋史の方が触れている本は、そう多くないのではないでしょうか。そのためか、本書では、まず「倭寇」という語について触れています。
著者は、「『倭』とは日本を指す漢字」であり、日本人の多くが知らなくても「外国人は現代も使わないわけではない」と述べています。確かに、わたしもニュースで見て、何と時代錯誤なことを・・・・・・、と思ったことがありました。
著者は、まず「『倭(=日本)』が『寇(=襲来)』する。海を越えてやってくる『倭寇』とは、『日本の海賊』『日本の脅威』というにひとしい」ことから、「以後のあらゆる日本との関係は、その『倭寇』とからめて表現された」といいます。例えば、豊臣秀吉の朝鮮出兵などです。そして現代のニュースなどまで――。
その「倭寇」という言葉の始まりは、『高麗史』の1350年2月の記事に「慶尚道の固城・竹林・巨済を襲撃した事件を『倭寇の侵、ここに始まる』と」紹介しています。
高麗王朝は、「倭寇」によって滅びたともいわれていますが、この頃東アジアには大きな変化が有りました。
1368(応安元、正平23) 朱元璋が明を興す。
1392(明徳3、元中9) 李成桂、朝鮮を建国。
1392(元中9、明徳3) 南北朝合一。
20数年の間に、東アジアでは、王朝の交代、政治体制の変化がありました。これに少し遅れて、
1429(正長2) 琉球の三山統一があります。
朝鮮半島と中国は地続きでもあり、古代から密接なつながりがありましたが、日本にとっても東アジア世界の新たな秩序を構築する必要性に迫られたのです。かつては、国レベルでは遣唐使、民間人レベルでは僧侶が入宋して仏教を学ぶなどのつながりでしたが、人口の増加や経済の発展もあり、日本にとっても大陸や半島との新たなつながりが求められたのではないかと思われます。
もともと中国、朝鮮と日本は海を介してつながっており、そこでは近代国家(領土、国民、主権)のように明確な国境は無く、かつ、国民も明確に帰属意識を持っていたわけではないでしょう。むしろ、「海を生活の場として共有していた」のではないでしょうか。そうした人々を「境界人」(注)と呼びました。そうした境界人が、東アジアの新たな体制の元、交易等密接なつながりを持つようになりました。ときに抗争や略奪等も起きます。そのことが、「倭寇」として認識されたということなのでしょう。主体が境界人ですから、倭人のみということでもありません。
本書では、「『倭』字の実質は、日本にとどまらず、ひろく海外と通じる華人・夷人であり、『寇』字の実質は、海賊にかぎらず、政権を信じず反乱も辞さない商業取引であった」としています。それが、日本史学でいうところの「倭人」「倭寇的状況」だというのです。この解釈に思わず引き込まれてしまいました。
さらには、そのことをより広汎に一般化して「海外と通じ独自の経済・ルールを有する場・集団ということになる」といい「場であれば密貿易のアジトばかりではなく、開港場・租界・植民地・租借地もふくみうるし、ヒトなら海賊・匪賊ばかりか、中央政府・既存体制から自立反抗する政治勢力・権力体にも転化しえた」として、明代以降の中国史を捉え直します。そこでは、孫文や国民党、中国共産党という「革命」勢力もまた「倭寇」になぞらえて説明されるのです。
この明代以降の中国の歴史の捉え直しは、たいへん魅力的で、現代中国のこれからに大いに興味をそそられます。そして、過去から密接につながってきた中国についての認識を新たにすることでしょう。ぜひ、お手にとってお読みいただければと思います。
本書の目次は以下のようになっています。
はじめに
第1章 「倭寇」をみなおしてみる
1 経過と言説
2 研究の進展
3 契機と過程
4 「倭寇的状況」をこえて
第2章 「互市」の時代
1 鄭成功
2 「倭寇」から「互市」へ
3 「倭寇」「互市」から「夷務」へ
第3章 近代史という「倭寇」
1 アヘン戦争と「条約体制」
2 「洋務」の展開
3 世紀末にあたって
第4章 革命とは「倭寇」
1 変法
2 孫文と「革命」
3 「革命」の進展
4 孫文という「倭寇」
第5章 「倭寇」相剋の現代中国
1 国民政府の時代
2 中華人民共和国
3 香港の履歴と運命
4 現代と「倭寇」
おわりに
(注)「境界人」(マージナルマン)という概念を日本中世史において積極的に展開された方は、村井章介さんです。氏は、日本中世史を孤立した島国の歴史ではなく、アジア全体の国際関係・交流の文脈で捉え直したことで知られています。
最後に海を舞台にした小説を一つご紹介します。
少し古いですが、『海狼伝』(白石一郎、文春文庫)です。第97回直木賞受賞作でもあります。