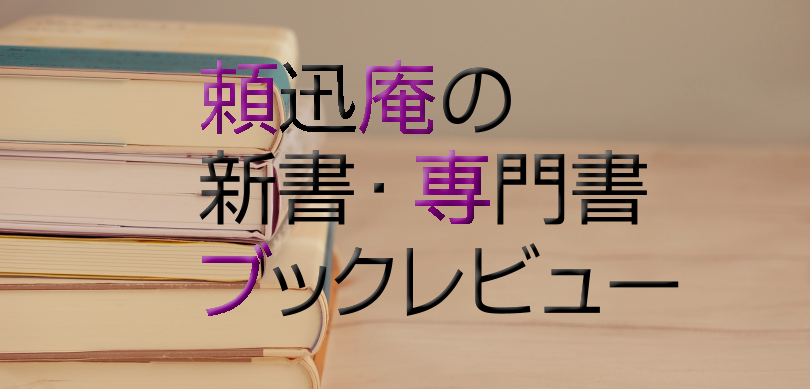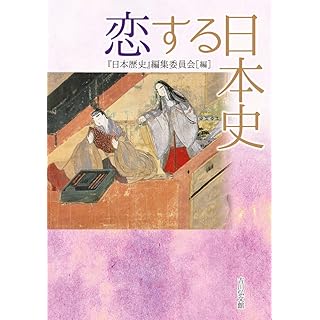『恋する日本史』
『恋する日本史』『日本歴史』編集委員会 (編集)、吉川弘文館
始めてこのタイトルを見たとき、日本史に恋した学者さんのお話かと思いました。
でも、違ったのです。日本史の各時代で恋愛がどのような形を取ってきたかを研究してものでした。
そのことを知ったとき、魅力的なタイトルに思えてきました。
「へえ。日本史の学会ってこんなこともできるんだぁ」
そのときの印象は今もはっきり覚えています。
しばらく、積ん読状態だったのは、わたしの上記のような勘違いのせいです(笑)
ところで、編集委員会の『日本歴史』とは何でしょうか?
『日本歴史』とは、日本歴史学会が編集する月刊雑誌(機関誌)のことです。「はじめに」によれば、その『日本歴史』2020年1月号に「『恋愛』にまつわる日本史の諸相を考察するという趣旨で、第一線の研究者の方々にご寄稿いただき」、新年特集「恋する日本史」を掲載したというのです。
その後、「編集委員会では、この特集の成果を学会・会員にとどまらず、広く社会に発信することを考え」て、本書を発行したということで、新たに8編程度追加されているらしいのです。
本書の目次は以下のようになっています。
古代
万葉びとの「恋力」 ―『万葉集』にみる非貴族階級の恋―
桓武天皇と酒人内親王
古代における内親王の恋と結婚 ―皇孫の地の世俗化―
「一帝二后」がもたらしたもの ―一条天皇、最後のラブレターの宛先―
摂関期の史料にみえる密通
古代にみる肖像恋慕の心性
古代史はLGBTを語れるか
中世
院政期の恋愛スキャンダル ―「叔父子」説と待賢門院璋子を中心にー
鎌倉時代の恋愛事情 ―『民経紀』と『明月記』からー
尚侍藤原頊子(万秋門院)と後宇多院
娘の密通、そのとき母は……
宮中の恋 ―室町後期の女房たちの出会いー
近世
大奥女中の恋愛事情
ある宮家の「恋」
駆落・心中と近世の村社会 ―村における恋のゆくえー
〈恋文集〉について
勤王芸者と徳川贔屓の花魁
近現代
天心・波津・隆一の三角関係と美術行政の展開
軍隊と恋愛
純血教育のゆくえ ―1950年代前半における文部省の考え方―
戦後後室と恋愛 ―天皇制「世論」と理想的結婚イメージとの関係性―
同性愛と近代
以上、古代から近現代まで22本の論文が収録されています。
論文ですので、しかつめらしいタイトルもありますが、「これは呼んでみたい」というタイトルもあるのではないでしょうか。
全部を紹介するわけにもいきませんので、古代・中世・近世から少しづつ紹介させていただきます。
古代については、史料の関係からかそれとも文明の未成熟のためか、なかなか興味深い関係は見いだせません。貴族女性は、基本的に顔出しNGですので、恋はもっぱらチラ見の想像力と和歌のみ。恋愛関係も初な印象です。
その中で、「古代史はLGBTを語れるか」という論文は、そもそもテーマを編集委員会から依頼されてのことだったようで、LGBTという概念のない古代のLGBTを論じなければならないご苦労が文中に顕れているように感じました。
ところで、ジェンダーの面からみると、古代の戸籍では、当然男女差がわかるように記されているようですが、律令以前に男女を分ける意識はなかったようです。その事例として『古事記』に記載のある欽明天皇の子が、男女にかかわらず「〇〇王」という命名であったことを上げています。
しかしながら、『日本書紀』では、男性の子を「皇子」、女性の子を「皇女」と表記しており、「一つの可能性として、王族の男女を書き分けなかった時代と、書き分ける必要が生じた時代という、二つの時代の存在を示唆している」のではないかと著者は問題提起しておられます。興味深い指摘ではないでしょうか。
ただ、この時代は、男女の区別は元服してからで、そもそも子ども時代は、男女の区別自体がなかったのではないでしょうか。(第62回参照)
中世では、院政期の恋愛スキャンダルとして、崇徳天皇が白河院と待賢門院璋子との間の子であるという説が取り上げられています。
室町時代になると、幕府が京都に開かれて、武家と公家が同一府内にいるとはいえ、史料の関係でしょうか宮中の恋がとりあげられています。この頃の「宮中の女房はおおよそ上﨟(上﨟局・典侍など)・中﨟(内侍など)・下﨟(伊予局・御乳人など)、女嬬などそれ以下の女官にわかれていた」ようです。
では、皇后や中宮などはどうなっていたのでしょうか。実は「天皇のキサキは14世紀南北朝時代以来立てられておらず、女房たちが天皇の子を産んでいた」ようなのです。
ところで、宮中に仕えた後に退出した女性はその後どうなったのでしょうか。「宮中の恋 ―室町後期の女房たちの出会いー」で確認してみてください。
近世は、時代劇でも取り上げられていますので、「駆落・心中と近世の村社会 ―村における恋のゆくえー」やよく知られた桂小五郎と幾松の恋愛など「勤王芸者と徳川贔屓の花魁」など気になるものがありますが、「ある宮家の『恋』」からご紹介します。
宮家の恋の前に堤栄長という公家の話が紹介されています。彼は若い頃にある女性を見初めるのですが、親の強い反対を受けます。そのため、粘り強く時間をかけてようやく迎え入れる支度が調いました。しかしながら、彼女は疱瘡にかかってしまい、それまでの美しい容姿が一変してしまいます。栄長の親はそんな彼女を気味悪がりますが、「男子たるものに二言はない」と、「彼女を予定通り迎え入れ、生涯養いともに過ごした」というのです。
さて、本論のある宮家の恋とは、有栖川宮職仁親王のことです。彼に仕える女房の花小路が宮家に仕える近習の磯村織部との密通が発覚します。この花小路という女性は、40才を越えていましたが、磯野織部は15才でした。
織部は長の暇、花小路は宮家の家臣にお預けとなり、その後大和国円照寺に永のお預けとなります。本来ならこれで話は終わるはずですが、病がちな親王のために宮廷に召し戻されます。
ところが、2年後再び密通事件が起こります。男は宮家の筆頭家臣中川主税頭、女は花小路(この頃は菖蒲小路と名乗っていた)だったのです。ちなみに、中川は33才、花小路は当然40才を過ぎていました。
中川は隠居、花小路は大和国中宮寺に永のお預けとなります。ところが、4か月後、病気療養ということで彼女は京都に戻ることとなり、さらに2か月後親王の看病のために宮邸へ召しだされるのです。
裏切られても裏切られても、なぜ親王は召し戻したのか、なぜ密通事件を起こしながらも寺院へのお預けという処置だったのか、その謎はお読みいただいて解いていただけたらと思います。
さて、「恋愛」という語が、優れて近代の言葉だということは有名なことです。哲学や文化と同じく近代になってから創出された単語です。それまでは、「恋愛」ではなく、「色」「恋」と呼ばれていました。
「恋愛」という語は、近代的自我確立を目指す知識人にとって魅力的な言葉でした。なぜなら、当時は家父長制によって結婚が縛られていたからです。しかし、男が女を、女が男を好きになることは、誰にも強制できません。恋愛は本来的に事由なのです。
「自由恋愛で、男女の意思によってのみ結ばれる」
それは、家父長制を打破する道であると近代知識人には思われたことでしょう。ゆえに、恋は情熱的で、達成されたときの充足感は計り知れないものがあったことと思われます。 とはいえ、多くの人が挫折したかもしれません。だからこそ、多くの小説で描かれてきたのではないでしょうか。
しかしながら、情熱的な恋愛によって結ばれた男女も、その後の長い人生をそのまま像熱的に過ごすことができたでしょうか。そうではないことの方が多いのではないでしょうか。
そして、なぜそうなるのでしょうか。それは、近現代を越えたこれからも問い続けられる問題なのではないかと思われます。
さて、小説の紹介ですが、本書には数多くの男女の関係が描かれていますので、気の利いた作品は紹介できそうにありません。
――事実は小説より奇なり
本書を読んで、皆さまの創作意欲が刺激されることを願ってやみません!