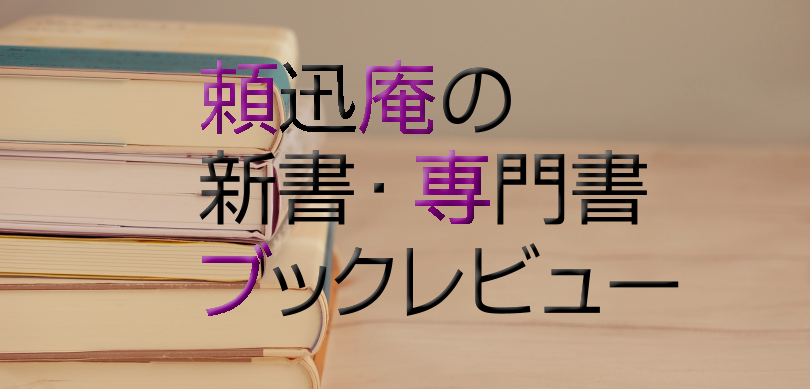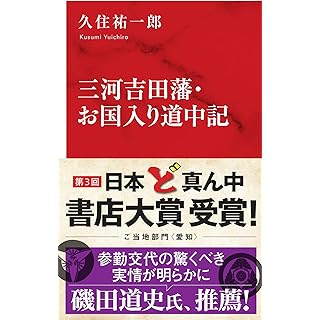『三河吉田藩・お国入り道中記』
(久住祐一郎・インターナショナル新書)
松平伊豆守信綱といえば、「知恵伊豆」として有名です。徳川三代将軍家光に仕え、老中として島原の乱の鎮圧、幕府初期の制度的安定に寄与したことで知られています。
信綱自身は、河越藩6万石(後に7万5千石)の大名ですが、子孫は三河吉田藩(現在の愛知県豊橋市)の大名となります。
信綱の子孫は、代々伊豆守に任じられますが、信綱から7代目の信明は、松平定信の後継者といってよい人物で、足掛け26年間にわたって老中を務めています。「寛政の遺老」と呼ばれ、幕政が比較的安定した時期でもありました。
この信明の子が
信順の子が信宝で、この信宝が、藩主になる前、若殿として始めて吉田にお国入りしたときの道中記をまとめたものが本書です。
さて、本書の主人公はもう一人居ます。大嶋左源太豊陳という人物です。彼の祖先は、信綱に従って島原の乱鎮圧に向かった家中100人の子孫であり、島原扈従の家として、松平家中では尊崇された家でした。
ただし、浮沈は激しく、300石の徒大頭から60石の目付まで、代々の当主によって差がありますが、何とか幕末、明治維新まで命脈は保ったようです。
その大嶋家の8代豊陳が、若殿信宝のお国入りの、現代で言う統括マネージャーを務めることになり、その取扱を記した古文書が残っていました。
本書は、その古文書を活用しながら、内側から見た大名行列の姿と懸命に働く江戸時代の武士を紹介したものです。
ちなみに、大嶋左源太の諱「豊陳」は「とよのぶ」と読むのではないかという方は、名前の読みにかなり通じた方と思われます。しかしながら、「とよつら」と読むのが正解です。その理由は……。本書を読んでいただければ、そのカラクリ(?)を知って、思わず時代を感じてしまうことでしょう。
いつものように、目次は以下のようになります。
はじめに
第1章 若殿と左源太
第2章 参勤交代アレンジメント
第3章 “サンキュー”におまかせ
第4章 必読! 参勤交代マニュアル
第5章 若殿様のお国入り道中
第6章 その後の三河吉田藩と大嶋家
おわりに
第1章は、若殿つまり松平信宝と左源太つまり大嶋豊陳の紹介です。
松平信順は、父信明のように老中まで務めますが、ストレスのためわずか2か月で辞任してしまいます。
老中を辞任したことで信順には、参勤交代の義務が生じるのですが、ストレスからさらに病になってしまい、なかなか回復しませんでした。そのため信順は、自分の代わりに息子の信宝を帰国させて、藩政の見習いをさせようと幕府に願い出ます。幕府からのOKがでて、信宝が国元へ帰国することになります。
このお国入りは、本来なら参勤交代で国元へ帰るはずの信順の名代で信宝が帰ることとなるため、参勤交代と同じ形態をとることとなりました。
そうした事情と参勤交代出発までが第2章で紹介されます。
ちなみに、アレンジメントとは、手配。準備、配置等のことで、経費のチケット制等現代的な感覚で、参勤交代の準備のことが述べられています。ですから、非常に読みやすいです。
第3章のタイトルの「サンキュ-」とは何でしょうか。
「サンキュー」とは人名で、三河屋久右衛門という人物の略称です。屋号の三河屋の「三」と名の「久」を合わせて「三久」つまり「サンキュー」というわけですで。
ただ、この場合「サンキュー」ではなく「サンキュウ」が適切だと思うのですが……。
閑話休題
この三河屋は、米屋という屋号も持ち吉田藩出入りの人宿でもありました。
人宿は、現在で言う人材派遣業ですが、参勤交代は人宿なしでは実行できないほどの人数が必要となります。
どれほどの人数かというと、今回の当初お国入りの人数345人のうち259人(75%)のほとんどが派遣労働者なのです。まさに「大名行列は派遣労働者でなりたっていた」ということになります。
この派遣労働者は、中間という「武家に仕えて雑事に従事した者たち」で、若党・草履取・陸尺・小者などと役割により区別されました。武家奉公人ともいわれました。
参勤交代だけでなく、通常も必要に応じて大名家に奉公しているのですが、どれくらいの割合で奉公していたのでしょうか。
本章の冒頭に、安永六年(1777)の吉田藩の調査結果が載せられています。それを見ると、江戸では士分210人、足軽231人、中間246人、国元(吉田)では、士分217人、足軽235人、中間79人となっています。国元(14.8%)に対して江戸では倍の38,8%となっています。江戸では、士分や足軽よりも武家奉公人が多いことが分かりますね。彼ら全員に人宿が関わっているわけではないでしょうが、やはりどこか、現代の正規社員、契約社員、派遣社員という区分を思ってしまいます。
第4章は、まさにタイトル通りの参勤交代マニュアルです。例えば、三百人を超す大所帯の宿割りをどうするのか? 宿泊予定の宿場で、他の大名とかち合った場合にどうするのか? 殿様が道中で病気になってしまったら……。
そういった場合の対処方法が述べられていますので、ぜひ、本書をお手に取っていただければ、現代の団体旅行とそれほど変わらない幹事の苦労が忍ばれることでしょう。
第5章は、いよいよお国入りの出発です。7泊8日の行程を1日毎に述べています。
参勤交代の道連れになったつもりで読んでみると面白いでしょう。
ちなみに、参勤交代で単に国入りにお供をしただけで、国元に着くとすぐに江戸へ引き返した面々がいたという事実を知ったのも本書での面白い発見でした。
さて、若殿お国入り後の吉田藩と主人公大嶋左源太の大嶋家はどうなったのでしょうか。
信明、信順と二代続けて老中となった伊豆守家ですが、若殿信宝は、藩主を継いでから老中となったのでしょうか。
さらに、幕末、明治維新を乗り切った松平家、大嶋家はどうなったのでしょうか。それは、本書第6章でお楽しみください。
参勤交代を扱った小説はいくつかありますが、事実は小説よりも奇なり……。
むしろ、本書を読んで参勤交代に関わる人間模様を様々想像するのも面白いかもしれません。