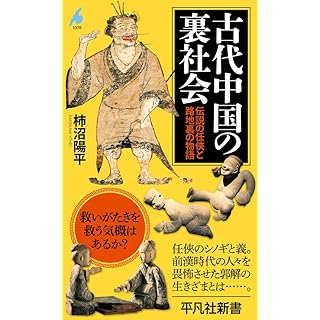頼迅庵の新書・専門書ブックレビュー61
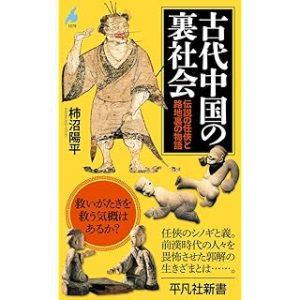 古代中国の裏社会: 伝説の任俠と路地裏の物語
古代中国の裏社会: 伝説の任俠と路地裏の物語
(柿沼陽平、平凡社新書)
久しぶりに日活版任侠映画『男の紋章』(※1)を観ました。
任侠映画というと東映ですが、日活(及び松竹)も作っていました。東映との違いは、主人公の職業にあります。『男の紋章』の主人公大島竜次は、医者から父の後を継いで博徒の親分になる(なった)のです。
東映の主人公は、博徒以外は、板前や露天商などいわば庶民階級なのに対して、大島竜次は医者という知識階級に属します。また、今は離縁していますが、実母も博徒の親分という設定です。そのため、日活版は親子の情が絡むことが多く、そのことが物語に深い陰影を与えています。
日本で任侠または遊侠(游侠)というと国定忠治や清水次郎長など博徒の大親分を思い浮かべる人も多いと思います。彼らも始めから大親分であったわけではなく、若い頃は、旅から旅へ男を磨いたものです。そんな渡世の世界を描いた小説を日本では、「股旅物」といいました。長谷川伸が開拓したものと言われています。
義理と人情に代表される博徒・渡世人の世界を描いた東映や日活の任侠映画は、非常に日本的な印象を受けますが、任侠・游侠の世界は、実は中国の方が、評価は高いのです。
なぜなら、司馬遷の『史記』に「游侠列伝」として当時の任侠、游侠の徒が述べられているからです。紀元前から任侠・游侠の徒がいたということも驚きですが、史書にそうした者たちの列伝が立てられたということも吃驚ですね。
司馬遷は、前漢の武帝の時代に生きた人物ですが、その頃中国には、〈郭解〉という任侠・游侠の大親分がいました。
本書は、その郭解という人物を通して前漢を含む古代中国の裏社会を叙述したものです。当時の任侠・游侠は、頼まれれば殺人も犯しましたので、法に従って生きる世界を表とするのに対して「裏社会」と形容しています。
中国の物語の世界では、例えば『三国志』の劉備、関羽、張飛の桃園の誓いは、任侠・游侠的だし『水滸伝』は、まんま任侠・游侠の物語といっても良いかもしれません。とはいえ中国史の分野では、通俗的ではなく学問的に任侠・游侠を取り上げたものがけっこうあります。
そうした書籍は、「任侠的人間を何人か史料から選び出してその生き様を列記し、そこから任侠の特徴を捉えようとするもの」が多いのですが、本書は郭解という当時「任侠の代表格ともくされていた」人物に焦点をしぼり、「その生涯をていねいに跡づけ、ひとつひとつの行為を検証し、そこから当時の任侠と、かれらの跋扈する裏社会の一端を浮き上がらせようとした」という意欲作です。(エピローグ参照)
本章は8章構成となっています。
プロローグ――古代中国の裏社会へ
第一章 暗殺の顚末
第二章 郭解の家柄
第三章 血塗られた経歴――「少年」から大任俠へ
第四章 ニセガネと組織犯罪
第五章 呉楚七国の乱と任俠
第六章 轟く俠名、武帝に届く
第七章 勅命との対峙
第八章 郭解の最期――そして伝説へ
エピローグ
第一章は、郭解の任侠の仕事が描かれます。なんと彼は、県令(日本では現在の市長相当か?)からの暗殺依頼を引き受けているのです。併せて、その鮮やかな手際が描かれます。
第二章は、郭解の家系が述べられます。由緒ある家系ではないようですが、『史記』によれば、母方の祖母が〈許負〉という人物で、秦末漢初に名を馳せた人相見だったようです。現代と異なり、古代中国では、政治の場で人相見はたいへん重宝されたようです。クライアントには、前漢文帝の生母薄氏がいたというのです。
第三章は、郭解の経歴が語られます。併せて、次ぎのようなエピソードが紹介されます。
ある日、郭解の甥が、酒場で刺殺されます。姉の子だったようです。当然姉は、我が子が殺されたので激怒します。犯人を捜し当てた郭解は、事情を聞き「悪いのは甥」だとして犯人を解放します。先に手を出したのが甥だったのです。こうした逸話は、郭解が単なる犯罪者ではないことを物語っていますし、任侠が何たるかを物語ってもいます。
余談ながら、中国に武侠小説(米2)という分野があります。義(大義)と情(愛情)に悩む任侠・游侠の武芸者(剣豪)を主人公とした物語ですが、特に優れた武芸者は「大侠」と呼ばれます。
第四章は、古代中国の任侠(游侠)を著者は、「人との約束事を重んじ、身命を賭して他人の窮状を救う義侠心を持つとともに、しばしば犯罪行為にも手を染める人たち」と定義しています。その犯罪行為の一つがニセガネ作りです。本章ではその実態が述べられています。
第五章は、前漢最大の内乱呉楚七国の乱(※3)を取り上げています。乱はあっけなく皇帝側(朝廷)の勝利に終わるのですが、その裏には任侠の助力があったというのです。こうなると、単なる「斬った、張った」の世界ではないですね。中国の任侠(游侠)はスケールが違います。
第六章は、郭解の活躍が前漢の武帝にまで聞こえていたこと、その世界が、郭解の世界と切っても切れない関係があったことが述べられています。まず、武帝の祖母竇太后から始まって武帝の衛皇后までの後宮の動きが説明されます。そして、衛皇后の従兄弟の衛青(※4)と郭解はつながりがあったというのです。
第七章は、茂陵という地へ移動することとなった郭解の送別会の席上、甥が県の下級役人〈楊掾〉を殺してしまったことによる騒動を描いています。郭解は捕まってしまいますが、朝廷からの使者の従者(儒者)と郭解の食客が揉めてしまい食客が従者を殺してしまいます。
第八章では、郭解の最後が描かれます。郭解の死は武帝の裁決によるものでした。しかしながら、大親分とはいえ、たかが任侠(游侠)1人の処分に、なぜ皇帝の裁決なのか。それは任侠と儒者との考え方の違いにありました。その謎は、ぜひ本書をお読みください。
ちなみに本書は、物語的な叙述になっていますが、注解をまとめて最後にし、併せて、図版等を多用するとともに細かいところまで実証しているユニークな構成となっています。
最後に、日本の任侠とは、「仁義を重んじ、弱きを助け強きを挫くために体を張る自己犠牲的精神や人の性質を指す語」(ウィキペディア)として定着しています。
一見、中国の任侠と似ていますが、大きな違いが2つあります。それは大きな犯罪に手を染めているかどうか、ということと国家的なことに関わるか否かということです。
これはどちらが良いか悪いかではなく、国土が広く他民族国家で、かつ国家が分裂興亡を繰り返してきた中国と、ほぼ単一民族で国家的な興亡のなかった日本との違いといって良いかもしれません。
最後に紹介する小説はこちら(↓)。
『花の歳月』(宮城谷昌光、講談社文庫)です。
第六章で取り上げられた竇太后と弟竇広国の物語です。没落した竇家から漢の後宮に入り文帝の妃となって景帝を産んだ竇氏、幼い頃に離ればなれになり、奴隷にまでなった広国と竇妃との感動の再会を描いた物語です。
(注)
※1 『男の紋章』とは、1963年公開された日活映画。監督:松尾昭典、脚本:甲斐久尊、出演:高橋英樹、和泉雅子、石山健二郎、名古屋章ほか、原案:紙屋五平。シリーズ化され10作品が制作された。YouTube(↓)で視聴できる。
米2 武侠小説とは、中国大衆小説の一つのジャンルで、武術に優れ義と情を重んじる主人公が活躍する小説の総称。清代前期以前を舞台とした作品が多く、日本の時代小説や任俠小説と多くの共通点を持っている。金庸、梁羽生が有名だが、特に金庸の豊かな教養と深い知識に裏打ちされた作品は、知識階級にも受け入れられているといわれている。小説に留まらず、映画やドラマ等でも取り上げられている。わたしは武侠ドラマが大好きで、語り出すと長くなるのでまたの機会に。
※3 呉楚七国の乱とは、中国前漢の紀元前154年に起きた内乱。皇帝の劉氏一族のうち、呉王、楚王、趙王、膠西王、膠東王、菑川王、済南王が起こした反乱。主力が呉兵と楚兵だったことからそのように呼ばれる。
※4 衛青(? – 元封5年(紀元前106年))は、前漢の武帝に仕えた武将。字は仲卿。爵位は長平侯。河東郡平陽県の出身。匈奴征討に功を上げた。