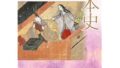第十二回 神宿る女――斎宮について
伊勢神宮には、内宮と外宮のほかに、「斎宮」というものがある。「さいぐう」と音読みすることが多いのだが、昔は「いつきのみや」と訓じていた。
斎宮はいまは存在しないのだが、斎宮跡とされる広大な遺蹟が残されている。
斎宮のなかにいる巫女のことを、斎王と呼ぶのだが、これも「さいおう」という音読みと「いつきのみこ」という訓読みが併用された。時には巫女そのものを、斎宮と呼ぶこともあった。
歴代の天皇は、皇女を伊勢の斎宮に派遣することで、自らも特別の立場の支配者であることを、世に示していた。
娘に神が宿る。それくらいだから、その親も、神さまに近い存在なのだ、というわけだ。
もちろん、天皇にも神は宿る。即位の時に、いまでも秘密の儀式をやっていて、「まとこおうふすま(真床覆衾)」と呼ばれる寝具の上に座していると、そこに神さまが降臨することになっている。
ほんまかいな、と思わないでいただきたい。
日本人であるならば、そんなこともあるかもしれない、と思っていなければならないのだ。
しかしこれは即位の時の儀式なので、ふだんはもっぱら、皇女や、おおくは皇女として生まれた皇后に、神が宿るということになっている。
いまでも、伊勢で大きな行事が催行される時には、斎宮の役割を、天皇陛下の妹ぎみが担当されることがある。あのお方は、すでに一般庶民のところに嫁いでおられるのだが、皇女がもっている神秘性は失われていないということなのだ。
皇族の女性には、神が宿る。
古来、そのように信じられてきた。
斎宮という制度の始まりは、垂仁天皇の皇女、ヤマト姫(倭姫)に始まる。
日向の国から東征して「日の本のヤマト」と呼ばれる奈良盆地に王朝を築いた神武天皇は、日の神を信仰していた。なぜ日の神を信仰したのかについては、すでに語った。宮崎市の海岸のある青島の向こうから日が昇るところを昔の人が見て、「アオッ」と叫んだとか、そういった話だ。
その日の神を祀る神社は、王都の纒向の近く、奈良盆地の東端の三輪山のふもとにあった。
三輪山というのは、国津神の王であった大国主の怨念がひそんでいるとされる。こちらは出雲系の神さまだ。
出雲系の三輪山のふもとに、日向系の日の神の神社がある。
これでは神さまどうしが反目するのではないか。そういう懸念から、日の神の神社を移設することになった。
神武天皇は日出ずる地を求めて瀬戸内海を東進し、大阪湾の果ての草香の地を「日の下の地」と定め、さらにもっと東の奈良盆地に王都を築いたのだが、奈良で暮らしてみると、太陽はやっぱり、東から昇ってくる。
もっと東の方に神社を移した方がいいのではないか。
そういうことで、新たな日出ずる地を求めて、旅が始まった。
主役は、日の神の巫女をつとめていた垂仁天皇の皇女のヤマト姫だ。
ヤマト姫の一行は、ついに陸地の東の端に到達した。その地は、宮崎と同じように、つねに海の向こうから太陽が昇ってくる。
伊勢。
まさに日の神を祀るにふさわしい地だった。
そこに伊勢神宮を建立し、ヤマト姫は斎宮となってその地にとどまった。
およそそういったことが、『日本書紀』などの歴史書に記されている。
ヤマト姫には重要な出番がある。
日本の歴史上、トップクラスの英雄ともいうべき人物として、「ヤマトタケル(尊称をつけて日本武尊と表記する)の名を知らない人はいないだろう。
ぼくが子どものころに見た『日本誕生』という東宝の映画では、三船敏郎が演じていたので、あまりイメージはよくないのだが、本当はヤマトオグナ(少年のようなやさおとこ)と呼ばれていたくらいだから、少女漫画で描かれるような美青年だった。
その日本武尊は父親の景行天皇から、うとまれていたようで、九州の熊襲征伐を命じられる。これには成功したものの、今度は蝦夷征伐を命じられて、東国に赴くことになる。
その東国への旅の途上で、日本武尊は伊勢に立ち寄り、叔母にあたる斎宮のヤマト姫と対面する。
巫女のヤマト姫には、予知能力があったようで、困った時にはこれを開けなさいと言って、守り袋のようなものをくれる。
伊勢神宮の御神体は八咫鏡だが、スサノオがアマテラスに献上した天叢雲剣も収蔵されていた。その神器の剣を、ヤマト姫は日本武尊に手渡すのだ。
スサノオが八岐大蛇を退治した時に、その体内から取り出したという魔法のアイテム。当時は三種の神器のうちの二種が、伊勢神宮に安置されていた。
日の神が天岩戸に隠れて日食になった時に、他の神々が岩戸の前で大騒ぎをした。それで日の神が岩戸の隙間からのぞくと、そこには鏡が置かれていて、自分自身の姿が映った。すなわち鏡は、アマテラスそのものを象徴している。
アマテラスとスサノオのウケヒによって、日向系の神話と出雲系の神話が合体した。その象徴として、剣も伊勢神宮に置かれていた。
その剣を携えて、日本武尊は東国に向かった。
それでは、ヤマト姫が渡した守り袋のなかに何が入っていたか。
それは火打ち石だった。そんなものが何の役に立つかとも思われるのだが、焼津のあたりまで来た時に、火打ち石が必要となる。
地元豪族の策略によって、草原で火攻めにあった時、日本武尊は自分の周囲の草を、神宝の剣で薙ぎ払い、自分の周囲に安全地帯を作ったあと、その周囲の草に火打ち石で火をつける。
すると野火は、策略を立てた敵の方に向かって燃え広がっていき、日本武尊は窮地から逃れることができた。
そのようなことがあったので、この剣は、その後は草薙剣と呼ばれることになった。
その剣はどうなったか。日本武尊は最後に伊吹の神と闘う前に、自らの死を覚悟していた。そこで彼は、婚約をしていた尾張のミヤズ姫(宮簀姫)に剣を托して、伊吹の神との対決に臨み、祟りを受けて没することになる。
その時に、足が腫れて「三重にくびれた」と嘆いたことから、その地を「三重」と呼ぶのだと伝えられる。
そういうわけで、神器の剣は尾張にとどまり、いまも熱田神宮に収められている。歴代の天皇が所有しているとされる剣はレプリカにすぎない。
源平合戦で安徳天皇が壇ノ浦に沈んだ時、剣も海に沈んで回収できず、大騒ぎになった。これは異母弟の後鳥羽天皇の即位にレプリカの製造が間に合わなかっただけのことで、大騒ぎするほどのことはなかったのだ。