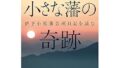第十七回 日本武尊とオトタチバナ姫
大幅に話が脱線したようなので、古代のテーマに戻したい。
今回は日本武尊について語る。
この人物の名前は、ヤマトタケルノミコトと読んでいただきたい。
日本武尊というのは日本書紀の表記で、古事記では倭建命となっているのだが、太古の日本には文字がなかったので、ヤマトタケルという呼称だけが人から人へ伝えられたのだろう。漢字の表記はあとから付けたものなので、どっちでもいいという感じだ。
ただ日本書紀では、神や貴人に対する「みこと」という尊称を、特別の偉い神さまは「尊」、その他は「命」と使い分けている。日本武尊は、特別の神さまという、最上ランクの存在なのだ。
しかしぼくはとりあえず、呼び捨てで、以後はヤマトタケルと呼ぶことにする。
ヤマトタケルは何をした人なのか。
父のタラシヒコ大王(景行天皇)は暴虐の覇王だった。のちの武烈天皇と同じくらい評判のよくない天皇だ。まあ、正義の味方のヤマトタケルと対比させるために、わざと父親の悪いイメージが語られたのだろう。
タラシヒコ大王の祖父の崇神天皇、父の垂仁天皇は、その名称のとおり、神々を手厚く祀ったり、仁政で世を治めたり、評判の高い聖王だった。
ところがタラシヒコ大王はそういうものを無視して、ひたすら冷酷な侵略を繰り返した。そのため祖父や父が半ばまで成し遂げた日本国の統一という夢が、瓦解してしまった。各地で反乱が起こったり、神の怒りに触れて疫病がはやったりした。
ヤマトタケルは父の命令で九州に赴き、クマソの英雄だったクマソタケルを倒した。死ぬ間際にクマソタケルは、自分を倒した英雄を称え、名を贈る。
それまで「少女のようなやさおとこ」という意味の、ヤマトオグナと呼ばれていたこの英雄が、ヤマトタケルと呼ばれるのはそれ以後のことだ。
ヤマトタケルは父のタラシヒコ大王から、嫌われていたようだ。息子の評判がよすぎるので、自分の地位を脅かされると考えたのかもしれない。九州から帰ったばかりのヤマトタケルは、今度は東国に派遣される。王都から追い払われたのだ。
東国に向かう途上、伊勢斎宮のヤマト姫から、神器の一つのアメノムラクモノツルギ(天叢雲剣)を託された話は、この連載のなかですでに述べた。焼津のあたりで地元の地方領主の策略に遭遇し、野原で火攻めになるのだが、足もとの草を剣で薙ぎ払い、ヤマト姫からもらった火打ち石で、迎え火を点けて敵を滅ぼした。
それ以後、この剣はクサナギノツルギ(草薙剣)と呼ばれることになる。
さて、ヤマトタケルには、三人の妻がいるとされる。のちの仲哀天皇を産んだフタジ姫(両道姫)、最後に剣を托すことになる尾張のミヤズ姫(宮簀姫)、東国への旅に同行したオトタチバナ姫(弟橘姫)だが、ここではオトタチバナ姫について語っておきたい。
焼津で火攻めに遭遇した時も、オトタチバナ姫はヤマトタケルのかたわらにいた。いっしょに危機を体験したのだ。
この焼津のあたりの野を、古事記では相武と記していて、相模のことかとも思えるのだが、焼津は駿河の国で、その近くに相良という地もあるので、そのあたりをサガミあるいはサガムと呼んでいたのかもしれない。
あるいは、東国の毛野(のちの上野と下野)の手前の広い地域をムサの国と呼び、そのムサの国の都に近い側を「ムサ・カミ」、遠い側を「ムサ・シモ」と呼んでいたのが、相模と武蔵になったという説もある。
だとしたら、伊豆や駿河まで含めて、のちの武蔵の国よりも手前の広い地域を、サガミと呼んでいたということだろうか。
さて、草を薙いで火攻めから脱出したあと、ヤマトタケルは三浦半島に到達した。いまでも横須賀市久里浜から対岸の富津市金谷にフェリーボートが出ているけれども、このあたりの浦賀水道は幅が狭く、古代から交通の要衝になっていた。
律令制の時代にフサ(総)の国が二つに分けられた時も、船で房総半島に渡るのが正規のルートだったので、手前が上総、その先が下総と呼ばれることになった。東京から総武線で千葉に向かうと、先に下総と呼ばれる駅名があるので、ヘンな感じがする。
ヤマトタケルも房総半島に渡ろうとしたのだが、この走水と呼ばれる浦賀水道には、荒ぶる神がひそんでいて、突然の嵐で船が沈みそうになった。
この時、妻のオトタチバナ姫は海に身を投じた。
荒ぶる神に対して、自らを生け贄としたのだ。
この時にオトタチバナ姫が詠んだ和歌が伝えられている。
〽さねさし相模の小野に燃ゆる火の、ほなかに立ちて問ひしきみはも
生け贄という概念は、太古の昔からあったと考えられる。
スサノオがヤマタノオロチを退治したのも、クシナダ姫という少女が生け贄として献げられそうになっていたからだ。オロチを退治したスサノオはクシナダ姫を妻とする。
クシナダ姫はのちに、その名を「櫛(奇し)稲田姫」と解釈し、稲作の守り神となって、茨城県や島根県の稲田神社に祀られている。
この生け贄の類は、中世くらいまではあったようだ。橋や堤防を築く時に誰かが人柱になる、といった伝説があるし、神が生け贄を要求する時に、生け贄となる娘の家に「白羽の矢」を立てるという伝説や風習が残っていた。
ヤマトタケルはオトタチバナ姫を深く愛していた。東国を去る時に、古事記では足柄峠で、日本書紀では碓井峠で、背後の東国の方を振り返り、「吾妻、はや」と嘆いたと伝えられる。「はや」は感極まった時に発せられる感嘆詞で、亡き妻を思って「ああ……」と詠嘆したのだろう。
このことから、東国のことを「あづま」と呼ぶようになったとされている。
東国を平定して、エゾの若者たちを配下に収めたヤマトタケルは、尾張に赴いて、もう一人の妻のミヤズ姫に、草薙剣を預ける。そのためこの宝剣は、いまも名古屋の熱田神宮に収蔵されている。
ヤマトタケルは最後に伊吹の神と対決して敗れ、足が腫れて「三重にくびれた」と嘆いて死んでいく。これが県名の由来なのだが、三重県に住んでいる人はそのことを知っているのだろうか。
ところで、ヤマトタケルはなぜ伊吹の神と対決して、死んでしまうのか。
突然だが、三島由紀夫の初期の作品に、『青垣山の物語』がある。
十七歳の時に平山公威という本名で書いて、未発表のままに残された作品だが、『季刊文科』(令和7年春季号)に掲載された鈴木ふさ子の論文によると、ヤマトタケルを主人公にした物語で、ここでは主人公が明らかに、イエス・キリストのように、自らを生け贄として神に献げたように書かれているということだ。
実はぼくも同じことを考えていて、二十年ほど前に『倭建』という作品を発表している。ここでもぼくは、ヤマトタケルをイエス・キリストになぞらえて、伊吹の神とウケヒ(誓約)を結んで神々と和睦し、日本国に平安をもたらしたといった話に仕立てた。
この本は売れなかったようで、担当編集者から、「主人公があっけなく死んでしまうような話はおもしろくない」と言われてしまった。その結果、続篇として書くつもりだった『神功皇后』の企画もボツになってしまった。ぼくのパソコンには、日の目を見なかった『神功皇后』の出だしの部分がいまもそのまま残っている。
確かに、古事記でも、日本書紀でも、ヤマトタケルはあっけなく死んでしまう。
英雄があっけなく死んでしまうところに、深い悲しみがある。
源義経だって、あっけなく死んでしまうではないか。
でも、なぜこんなにあっけなく死んでしまうのか。
古事記を読んでも、日本書紀を読んでも、なぜヤマトタケルが死ぬことになるのか、よくわからないのだが、最愛のオトタチバナ姫が生け贄として身を投げ、そのことによって荒ぶる神を鎮めたのを見て、ヤマトタケルは自らも生け贄として死ぬ決意をしたのではないかと、ぼくは考えた。
若き三島由紀夫も、同じことを考えたのだろう。ぼくはこの三島の作品のことはまったく知らなかったので、アイデアを盗用したわけではない。
ともあれ、ヤマトタケルにとって、オトタチバナ姫は最愛の妻であり、ヤマトタケル自身の生き死ににも大きく関わった女性だということはいえるだろう。