頼迅庵の新書・専門書ブックレビュー60
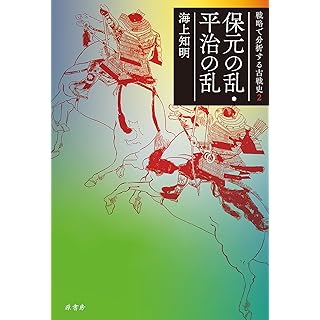 保元の乱・平治の乱 戦略で分析する古戦史2
保元の乱・平治の乱 戦略で分析する古戦史2
海上知明、原書房)
本書は、古代から中世への変革期、貴族政治から武家政治への過渡期に発生した保元の乱及び平治の乱について書かれたものです。
しかしながら、いわゆる歴史の専門書等とは異なり、副題にある通り、戦略で分析した保元の乱及び平治の乱を取り上げています。
では、戦略の分析から取り上げた保元の乱及び平治の乱はどのようなものなのでしょうか。
本書の目次は、以下の通りです。
第1章 軍記物語の利用法
1 軍記物語と史料の問題
2 『保元物語』と『平治物語』
3 覇権循環論と戦争、そして政治変動
4 衛兵政治としての「武者の世」
5 戦略と戦術
6 『孫子』
7 『戦争論』
8 『孫子』と『戦争論』の対比
9 弱兵と強兵
第2章 「保元の乱」
1 軍記物語の描く「保元の乱」
2 平家の台頭
3 乱前の社会情勢
4 複合された対立
5 政略上の勝敗
6 大戦略と軍事戦略
7 「保元の乱」勃発
8 「保元の乱」の戦闘経緯と検証
9 戦後処理
10 河内源氏の血の粛清
11 恩賞問題
12 過渡期
第3章 「平治の乱」
1 軍記物語の描く「平治の乱」の顛末
2 権力抗争
3 「平治の乱」勃発と黒幕を巡る諸説
4 頓挫したクーデター
5 不意をつかれた清盛
6 大戦略的対応
7 政治的対応
8 戦略的対応
9 前線の指揮官・平重盛
10 戦術的対応
11 平家政権への道
12 結論
本書は3章構成となっています。
第1章は、保元の乱、平治の乱を戦略で分析する前に、まず使う資料として、なぜ軍記物語を使用するのか、そして軍記物語を利用して分析するためのツールと方法論が示されます。
軍記物語は、いわゆる物語であり、当然フィクション取り混ぜての内容になっています。そのため、当然歴史学では一次史料として扱わないのが常識となっています。
ですが本書では、例え軍記物語でも、いや軍記物語であるからこそ、
① 合戦の骨格的なこと、大筋はつかみとることができること
② 同時代の日記等一次史料を下敷きにしてそこにある法則や原則を把握できること
から、軍記物語、今回の場合は『保元物語』『平治物語』を使うこととしたことが述べられています。
要するに大まかな合戦の流れは、軍記物語でなければ把握できないだろうという趣旨だと想われます。
ところで、「戦略」と同時によく使われる言葉に「戦術」があります。この二つはどう違うのでしょうか。
著者は、「戦略」は軍全体の動きで、現在ではさらに3つに細分化され、「戦術」は目の前の相手に対応した個々の動きであると整理します。
そして、「戦略」と「戦術」を体系化すれば、
「大戦略―軍事戦略―作戦戦略―戦術」ということになると定義しています。
さらに、クラウゼヴィッツと孫子という東西の戦争論の第一人者の戦争哲学書を分析ツールとして保元の乱、平治の乱を社会科学的に分析する方法論が示されます。
第1章は、単なる戦争論を越えて、社会科学としての戦争論になっています。著者の方法論の展開といっても良いでしょう。理論的で難しいところもありますが、その内容は知的刺激に富んでいます。
いわゆる歴史家の「歴史科学」とは異なる視点に魅力を感じるのは、わたしだけではないと思います。
第2章及び第3章は、第1章で述べられた方法論を用いて、『保元物語』『平治物語』等を用いての分析となります。
周知のように、保元の乱、平治の乱は、古代から中世に変わる歴史上の節目として捉えられる合戦です。具体的には、武士の登場とその武力無しには、権力争いに勝利できなくなったということになります。
武士は、その発生から開発領主が武装したものと軍事貴族(京武者)とに大別されます。いわゆる清和源氏(本書では「陽成源氏」説を採用。その理由はぜひ本書をお読みください。)のうち早くから藤原摂関家に近づいた河内源氏と始め開発領主でしたが、平将門の乱平定に功のあった平貞盛の子孫は、伊勢国、伊賀国に勢力を扶植して院に近づいていきます。
武力が古代の軍隊からどのように武士へ移っていったのか、武士がどのように発展したのか、第二章ではその概括も述べられていてたいへん参考になります。
古代政治は、摂関政治から院政へと権力の移行が進んでいました。同時に摂関家、天皇家(当時は「王家」といいました。)ともに権力を巡る対立も生じていました。
天皇家では、鳥羽法皇の院政時に子の近衛天皇が亡くなります。次の天皇に鳥羽法皇の子である崇徳上皇は、我が子(重仁親王)の即位を望みますが、鳥羽法皇の寵妃美福門院の阻止で崇徳上皇の弟の後白河天皇が即位します。ここに崇徳上皇と後白河天皇・鳥羽法皇の対立が生じます。
一方、摂関家も関白藤原忠通と左大臣藤原頼長兄弟の対立が激しくなっていました。二人の父忠実は頼長を贔屓して藤原家の氏長者に任じます。
藤原頼長は、崇徳上皇と組み河内源氏の総帥源為義を味方につけます。伊勢平氏のうち平忠正等も頼長方となっています。その軍勢は、およそ一千余騎でした。
一方後白河天皇・鳥羽法皇は、伊勢平氏の平清盛、河内源氏の源義朝、摂津源氏の源頼政等を味方につけます。その軍勢は、一千七百余騎以上。
この両者が、勝敗を武力で決着をつけたが保元の乱です。
保元の乱で勝利した後白河天皇でしたが、乱後藤原信西と藤原信頼という二人の近臣の対立が激しくなります。
信頼は保元の乱の恩賞に不満を感じていた河内源氏の総帥となっていた源義朝を味方につけます。そして、平治元年12月、平清盛が熊野権現へ参詣に行っている隙を狙って500余騎で挙兵し、上皇となっていた後白河と二条天皇を幽閉します。そのことを知った清盛は、直ちに京へ戻り義朝と対決します。
これが平治の乱の概略ですが、権力の頂点にいる者同士が争った保元の乱は、その決着が武力に依っていたのに対し、平治の乱は、武力を持って強引に権力の頂点にある者の側近が、自分の意を通そうとして起こしたものでした。つまり武力があれば、自分が権力を持つことも可能だと知らしめた内乱であり、実際、乱後平清盛は、その武力を背景に自ら統治を行うようになり、ここから中世が始まることとなります。
以上を念頭に、保元の乱、平治の乱について著者の縦横無尽な戦略分析をお楽しみください。
保元の乱は、1日(一晩)で決着がついてしまいましたので、戦略分析が難しいところもありますが、平治の乱はそうではありません。
従来の歴史叙述では、評価されていた人物が、戦略分析からみると批判の対象となったり、評価されていなかった人物が、逆に実は傑出した人物だったりとその鮮やかな変転に息を飲むことでしょう。
併せて、著者は戦略家としての平清盛を非常に高く評価していますが、その理由も本書を読めばご理解いただけることでしょう。
長くなりましたので、関係書の紹介は省略させていただきます。


