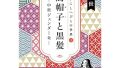第三回 小倉百人一首の一番歌
鎌倉時代の半ばに藤原定家が編んだ『小倉百人一首』は、誰でも知っているだろう。
カルタとしてばらばらにしてしまうとわからないのだが、あれには順番がある。
一番歌は天智天皇、二番歌は持統女帝ということになっている。
それはなぜか。
ちなみに終わりの方はわかりやすい。
九十九番歌が後鳥羽院、百番歌が順徳院。
二人とも、承久の乱で島流しになった天皇だ。
流罪となった二人をあえてベスト百のなかに加えたところに、選者の政治的意図と、心意気のようなものが感じられる。
ではなぜ天智天皇が一番歌なのか。
それは持統女帝の時代に側近として台頭し、律令制度を確立し、『古事記』『日本書紀』を編纂し、藤原京(父の中臣鎌足の晩年の住居があり藤原という氏姓の由来ともなった場所)への遷都にも功績のあった藤原不比等こそが、藤原一族の繁栄の礎となった人物であったからだ。
いや、これではなぜ天智天皇が一番歌かの理由にはなっていないので、もう少し不比等についての説明が必要だろう。
藤原不比等の偉大さはそれだけにとどまらない。
不比等は、娘の宮子を文武天皇に嫁がせて、宮子が産んだ聖武天皇の外戚(母方の祖父)となった。
天皇の母方の祖父が政権を独裁するというのが、平安時代に全盛期を築いた藤原一族の「外戚政治」というシステムだが、それは藤原不比等に始まっている。
その藤原不比等には、天智天皇の落胤であるという風評があった。
確かに『興福寺縁起』『大鏡』などに記されていることではあるが、興福寺は藤原一族の氏寺だし、『大鏡』も藤原一族の隆盛のようすを描いた歴史物語なので、史実としては信憑性がうすいとされている。
藤原一族の人々にとっては、平や、源と同様、自分の先祖も天皇だったらいいのに……、という願望から、一族の間にこのような風評が広まったと考えることもできる。
藤原定家が天智天皇を一番歌に置いたのも、彼が傍系とはいえ、藤原一族だったからだ。定家もこの風評を大事にしていたのだろう。
ただこの落胤説、根拠がまったくないわけではない。
藤原不比等の父は、大化改新で功績のあった中臣鎌足だ。
当時は蘇我一族が、皇極女帝を擁立して、独裁政権を築いていた。
宮中で三韓の使者を迎える公式行事の最中に、のちに天智天皇となる中大兄皇子と、中臣鎌足、そして同じ蘇我一族の石川麻呂(持統女帝の母方の祖父)は共謀して、大臣の蘇我入鹿を殺した。
不意打ちのクーデターであり、血なまぐさいテロ事件だった。
皇極女帝は退位し、弟の孝徳天皇が擁立された。
中臣鎌足は孝徳天皇のもとで、内臣という高い地位を与えられた。
『万葉集』には、鎌足が孝徳天皇から愛人の安見児という女官を下げ渡され、喜んで詠んだ和歌が掲載されている。
〽吾はもや安見児得たり皆人の得かてにすとふ安見児得たり
(わたしば安見児さんを貰い受けました。誰もがほしがったあの安見児さんを)
誰もが欲しがる美人の女官を貰い受けて大喜びしているさまが見てとれる和歌だが、どうやらその女官は、孝徳天皇の子を孕んでいたようだ。
生まれた男児は、子どものうちに仏門に入り、定恵という僧になって、留学僧として唐に渡った。
その定恵が、帰国の直後に謎の死を遂げている。定恵には、孝徳天皇の落胤という風評があった。謎の死も、そのことと関係があるのではと考えられている。
同じことが、天智天皇の時代に、もう一度、起こったのではないか。
不比等の母親は、『興福寺縁起』では「鏡王女」ということになっていて、鎌足の死後、彼女が夫の供養のために建てた山科寺が、のちに興福寺となった。
だから藤原一族の母といってもいい存在だ。
この「鏡王女」というのは、固有の名前ではなく、姓名不詳の「鏡王の娘」という意味だと考えられる。
有名な宮廷歌人の額田女王も鏡王の娘なので、二人は姉妹ではないかというのが通説だが、ぼくは同一人物と断定して作品を書いている(『白村江の戦い』『人麻呂しのびうた』など)
よく知られているように、額田女王は天武の愛人として十市皇女(大友皇子の妃)を産んだのだが、やがて天智の愛人となった。
もしも鏡王女と額田女王が同一人物なら、天智天皇から中臣鎌足に、下げ渡されたことになる。
孝徳天皇から孕んだ女官を下げ渡された前例があるので、同じことがくりかえされたのではと、のちの藤原一族の人々は考えたのだろう。孕んだ女を下げ渡されることは、配下にとっては名誉だったようで、平清盛も白河天皇の落胤だとされている。
まあ、そんな感じで、不比等の場合にも、天智落胤説が生じたのだ。
この説が正しいとすると、不比等は持統女帝の異母弟ということになる。
持統女帝は不比等を寵愛し、自分の実子で天武の後継者と定められた草壁皇子の舎人に起用している。
その草壁皇子は即位することなく病没したのだが、子息(持統にとっては孫)の文武天皇の擁立まで、長く続いた持統女帝の政権を、不比等は側近として支えた。
持統上皇が亡くなったあと、文武天皇も早世したため、文武の母親の元明女帝が擁立される。
元明は持統の異母妹でもあるが、母親どうしが姉妹で、同母妹に近い間柄だ。いずれにしても、天智天皇の血を引く皇女だ。
天皇が夭逝するという危急の場合に、「神宿る皇女」が政権をになうというのは、推古女帝以来の伝統だった。改めて語ることになるが、それ以前にも、神功皇后、飯豊青皇女、手白香皇女などの先例もある。
平城京を築いた元明女帝のあとも、娘の元正が皇位を継承し、ようやく文武天皇の子息の聖武天皇の時代になっても、病弱だった聖武天皇に代わって、不比等の末娘の光明皇后が政務をになった。その政権は娘の孝謙女帝に引き継がれる。
奈良時代は、女帝と皇后の時代であった。
まさに「女が築いた日本国」というテーマの最も輝かしい実例が、奈良時代だった。
こうした女帝の時代を築きあげたのも、持統女帝が独裁政権を築いたことが基礎となっている。
〽 秋の田のかりほの庵の苫を荒みわがころも手は露に濡れつつ
(刈り入れが終わった稲藁でできた苫屋は雨漏りがして濡れてしまいました)
この天智天皇の一番歌を、稲藁で作った庵のなかで天智が額田女王と逢い引きをしている(結果として不比等が生まれた)と考えてみよう。
〽 春すぎて夏来にけらし白たへのころもほすてふあまの香具山
(香具山の巫女たちが衣を干しています。この国に春をもたらした父の時代が終わり、わたしの夏が来たのですね)
持統女帝の二番歌は、藤原京遷都を成し遂げた皇居の高楼から、持統女帝が香具山を眺めている場面を思い浮かべていただくと、その意味の重さがわかる。
万葉集には、天智、天武、額田の三角関係を詠んだ長歌が収められている。
〽香具山は畝傍を愛しと耳成と相あらそひき……
ここでは大和三山のうち、天智を香具山、天武を耳成、額田を畝傍にたとえている。
すなわち皇居の上から持統が眺めている香具山は、父の天智を象徴しているのだ。
父の業績を乗り越えて、いま自分が藤原京という広大な王都を完成させた。夫の天武とともに反乱を起こし、天智の長男の大友皇子を殺して政権を奪取した自分は正しかったのだという、高らかな宣言がここにこめられている。
そしてかたわらには、異母弟で側近の藤原不比等が控えていたはずなのだ。