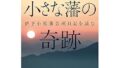第十六回 源平合戦とは何か
前回、平将門の話をした。
ぼくは御茶ノ水に住んでいるので、神田明神はすぐ近くだ。
正月になると、日本橋の企業の社員たちが、大挙して神田明神に押しかける。神田祭のお神輿も、そうした企業の社員たちが担いでいる。
これほど多くの人々に慕われている神田明神の祭神が、平将門であることは、誰もが承知している。
まあ、判官びいきという言葉があるように、人々は支配者となった頼朝よりも、負けた義経を愛している。同じように、平将門も愛されているのだろう。諏訪神社の祭神も、天界の軍勢と戦って逃げ出した建御名方だし、天神満宮の祭神は、左遷されて大宰府で無念の死を遂げた菅原道真だ。
平将門が、小領主であったことはすでに述べた。
同じように小領主が起こした反乱がある。伊豆の小領主だった北条一族が、伊豆の国司長官として赴任した平家の郎党を討った反乱だ。
ここから源平の合戦が始まったとされている。
平家の配下の郎党とはいえ、国が任命した正式の国司長官を殺したのだから、北条一族はいわば指名手配の犯人で、討たれて当然だった。
北条一族は、源頼朝を旗頭に擁立していた。後白河院の子息の以仁王の宣旨なるものも掲げていた。しかし頼朝は島流しになった犯罪者であるし、以仁王も平家に反乱を起こして殺されていた。
同じように地方の小領主が起こした反乱でありながら、なぜ平将門は鎮圧され、北条一族の反乱は成功したのか。話は大幅に横道に逸れてしまうけれども、この問題を考えてみよう。
源平合戦と言い習わされてはいるのだが、この闘いは源氏と平家の闘いではない。
国家権力の中枢にいた平家に対して、東国の小領主たちが百姓一揆のような形で起こした反乱が、出発点だった。
将門が平氏を名乗っていたように、北条一族も平氏だったし、北条に味方した千葉、畠山、梶原、三浦なども平氏だった。従って、源平合戦というよりも、中央の平家(清盛が公卿となったため一族は平氏ではなく平家と呼ばれた)と地方の平氏による合戦だった。
中央の「平家」と、東国の「平氏」の闘いだから、「源平合戦」ではなく、「平平合戦」と呼ぶべき戦さなのだ。
将門の場合と違っていたのは、将門の周囲の親戚の平氏たちがが、朝廷が派遣した追討軍に加わり、将門が孤立無援だったのに対し、北条一族の反乱には、東国の多くの小領主が味方したことだった。
確かに東国で人気のあった八幡太郎義家の末裔の源頼朝を旗頭にしたということも勝利の一因ではあったが、もっと大きな成功の要因があった。
東国の小領主たちは、切実な危機感をもっていた。
ここには荘園制度というものが関わっている。荘園は朝廷が打ち出した生産性向上の施策で、当初は荒れ地を開墾したものに一代限りの無税の恩典を与えたのだが、開墾の労力のインセンティブとしては不足していた。
そこで三代にわたっての無税の特典を与えたのだが、それでも開墾が進まなかったので、新規に開墾した田畑は、永年にわたって無税とした。ただし乱開発を防ぐため、荘園を開発できるのは藤原摂関家や、東大寺、伊勢神宮などの有力寺社に限ることとした。
この制度には抜け道があった。地方の小領主が荒れ地を開墾しても、摂関家の名義にすれば無税の恩典が受けられる。すると荘園は急速に広がったのだが、新たに開設された用水などは荘園の田畑にしか届かないので、税のかかる昔からの班田は生産性が低く、税を払えない農民は夜逃げをすることになる。
流出した農民は新田開発の労働力となり、荘園はますます増大することになる。一方、税のかかる田畑は農民が流出して荒れ地となった。朝廷の税収が減るのに対し、摂関家には名義料が入る。こうした名義だけの荘園は不正であったが、不正を摘発する国司の長官の任免権を摂関家がもっているため、国司は不正を摘発できない。
これが平安時代の摂関家の隆盛をもたらし、朝廷の財政が破綻する原因となっていた。
宇多天皇が菅原道真を右大臣に任じて、不正な荘園を摘発する「荘園整理」を試みたことがあったが、道真の左遷で頓挫することになる。
この「荘園整理」を大幅に断行したのが白河天皇だった。白河天皇(のちに上皇・法皇)は武士を国司の長官に任じて、武力によって不正な荘園を摘発した。このことによって朝廷の財政は豊かになり、摂関家の衰退を招いたのだが、平家もその過程で蓄財し、やがて政治の中枢に昇っていく。
国司の長官は、兼任が許されなかったのだが、平清盛は弟や子息だけでなく、配下の郎党を国司の長官にすることで、平家の支配地を増やしていった。
瀬戸内海の海賊退治で戦功を挙げた平家は、中国地方から九州、近畿など、西日本で勢力を伸ばしてきたのだが、その勢いは東国にまで及び、ついに伊豆はもとより関八州に平家の郎党が国司の長官として派遣されることになった。
関東地方は水害の多いところだが、東国の小領主たちは、堤防を作って水害を防ぎ、湿地帯に溝を掘って水を抜き、荒れ地には用水を通して田畑を広げてきた。これらは荘園として登録されてはいたが、平家の郎党が派遣されると、不正な荘園として摘発されるおそれがあった。
もう一つ、東国の小領主には懸念があった。
日宋貿易の利権を独占した平家は、大量の宋銭を輸入していた。
日本でも富本銭、和同開珎など、銅銭を鋳造した歴史はあるのだが、鋳造技術が未熟ですぐに壊れたり、磨り減ったりして、使い物にならなかった。
中世には「ビタ一文」という言葉が使われるようになったのだが、これは国産の銅貨のことで、磨り減っていることが多く、宋銭の半分以下の価値しかなかった。
宋は重商主義の国家で、物流の促進と貨幣経済の確立で、国を富ませてきた。そのため貨幣の鋳造技術が進み、信頼度の高い宋銭を大量に鋳造して、経済を発展させていた。
平家はそこに目をつけて、わが国でも貨幣経済の促進を狙っていた。
それまでのわが国では、交換価値をもつ資産は米だった。しかし買い物をするのに米俵を運んでいくわけにもいかない。そこへいくと、宋銭は一文、二文の少額の取引に使えるだけでなく、穴が開いているので、ヒモを通して束ねておけば、百文、千文の高額通貨としても利用できる。
すでに近畿や西国では、輸入された宋銭が出回り、貨幣経済が広まっていた。
貨幣の利用価値が高まると、とりあえず物を売って貨幣を蓄財したいという動きが起こる。ひところのビッドコインのような状態となって、宋銭の価値が高まり、宋銭で買える物の値段が下がっていく。いわゆるデフレだ。
デフレになれば、米の値段も下がってしまう。
東国の小領主が恐れたのは、東国にまで宋銭の流通が広まれば、自分たちの資産である米の価値が半減してしまうのではないかということだった。
そういう懸念があったところに、東国の各地に、国司の長官として平家の郎党が赴任することになった。危機感が高まった。
そこに、伊豆の小領主が武装蜂起して、国司の長官を殺す、という事件が起きた。
北条一族は、伊豆のなかでも、大庭一族の配下となっている小さな武士集団にすぎない。だが、流人の源頼朝を娘婿にして、果敢にも国家権力に敵対する騒動を起こした。
伊豆の国司を襲った段階では、北条一族は平将門と同じ逆賊だ。石橋山の戦いでボロ負けになって、小舟で房総半島に逃げた。
しかし頼朝と北条一族が房総半島をぐるっと回って武蔵国の手前まで来た時には、東国の小領主たちは各地の国司の館を襲って、その足で頼朝のもとに馳せ参じた。
娘婿の源頼朝を旗頭にしたというところに、北条一族の成功の秘訣があったことは確かだが、そこにはのちの尼将軍、北条政子の存在があった。
女が築いた日本国という連載のなかで、尼将軍政子の存在は欠かせないテーマではあるのだが、これについて述べるのは、ずっと先のことになりそうだ。